23年前に青年海外協力隊に参加したのをきっかけに、アフリカの医療協力を続けている、東京女子医科大学の杉下智彦教授。成人のHIV感染症罹患率39%という、当時世界で最も深刻な医療現場の最前線で活動した経験は、自身が医師を続ける上でターニングポイントになったといいます。
杉下教授がアフリカで見た医療の現実、そして、そこから学んだこととは?
現在も2ヵ月に1度はアフリカやアジアの新興国に赴き、活動を続けている教授の熱意の源を語っていただきました。
執刀した手術は3,000例以上。
マラウイにいた3年間は人生の中で一番働いた時間


- 杉下先生がアフリカに興味を持つきっかけは何だったのでしょうか?
中学生のときにアフリカの飢餓のニュースをテレビで見て、とってもびっくりしたんです。自分は死ぬことなんて考えずに生きている一方で、テレビの向こう側では自分と同じくらいの年齢の子が今にも死にそうになっている・・・。地球って、もうちょっといい所だと思っていたのに、どうやらそうではないらしい。
そんな現実があるのに、「何でそれをみんな放置しちゃっているんだろう?」と思ったとき、自分は医者になって、そういう国の人たちの健康問題に取り組めたらいいなと思ったんです。それで医学部に入り、外科医になりました。

- その後、日本でお仕事をされていた中でアフリカへ赴任されるわけですが、赴任先にマラウイ共和国を選ばれた理由は?

当時、青年海外協力隊で医師の募集をしていたのがマラウイ共和国だけだったんです。
とはいえ、そのころの南部アフリカから東アフリカにかけては、HIVの感染率がピークになっている時期で、私が赴任することになったマラウイ南部のゾンバという地方都市も、成人の罹患率が39%、3人に1人以上がHIV感染症を患っている状態でした。周囲からは、赴任することを止められましたが、そういった最前線の医療現場で自分を試したかったし、私が医者になる動機がアフリカでしたから、行くという決心は変わらなかったですね。

- 実際に行ってみて、現地の様子はいかがでしたか?

▲[杉下先生ご提供写真]アフリカ赴任中に執刀する杉下先生
本当に一からのスタートでしたね。ゾンバでは私が行くまで外科医がいなかったので、それまで手術をしていなかったんです。ですから、まずは外科チームを立ち上げて、手術室を整備することから始めました。吸入麻酔薬の気化器をコカ・コーラの缶で作ったり、地元のクリニカルオフィサー(※1)や看護婦さんたちに基本的な衛生概念や手術主義、周術期管理(※2)を教え、医療機材を集め、滅菌消毒などの環境を整えたりして、手術ができる体制を作りました。まさに野戦病院です。そうしたら患者さんがどんどん集まるようになって、毎日さまざまな手術を行うようになりました。私の赴任中に、全身麻酔の手術だけでも3,000例以上。あの3年間は、人生の中で一番働いた時期ですね。
(※1) クリニカルオフィサー:医師ではないが、診断や治療などの医療行為を行う資格を持つ医療スタッフのこと。準医師。
(※2) 周術期:手術の前後を含む一連の期間のこと。
アフリカの医療は、
宗教的・伝統的な価値観を大切にしないと説明できない

▲[杉下先生ご提供写真]アフリカ赴任中の杉下先生と現地の方々

- 3年で3,000例以上というと、朝から晩まで寝る間も惜しんで働かれていた感じですよね。
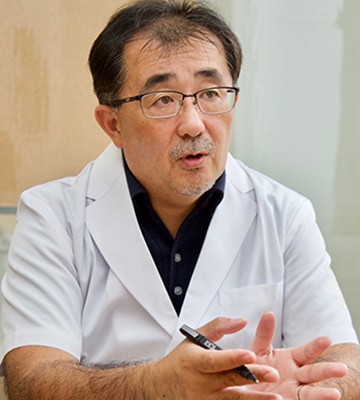
そうですね。携帯電話がない時代でしたので、ほとんど病院に泊まっていました。でも、最終的には自分が燃え尽きてしまったんです。私がどれだけ一生懸命働いても、患者さんは減らないどころかどんどん増える一方で。そのときに、「病気を治すのではなく病気にならない社会を作らなければならない」と強く願い、ハーバード大学公衆衛生大学院に留学して公衆衛生学を学びました。また、まさに地を這うような実践を通して、「伝統医療」が人々の心に深く根付いていることを痛感しました。そのような経験から、アフリカの伝統的な社会構造や世界観を知りたいと思い、ロンドン大学アジア・アフリカ研究大学院で医療人類学を学びました。

- マラウイの伝統医療というのはどういったものなんですか?
薬草を使った医療、私たちでいうところの漢方みたいなものです。例えば、マラリアの「キニーネ」や心不全の「ジギタリス」などは、元々植物から抽出された物なのですが、マラウイにも薬草を体系的に扱って治療を行う薬草師がたくさんいました。と同時に、社会規範の基礎となる「呪い」の概念があるので、身体的な疾病ばかりでなく、失敗して悔しいとか、失恋して淋しいといった精神的な症状に対してもしっかり手当てできることが現地の人にとっては重要なんです。マラリアに罹った人に対して、「あなたはマラリアだからこの薬を飲んでください。なぜなら、検査をしたら原虫が血液にいたからです」と説明をすると、相手はだいたい「そんなことはわかってます」と言います。そして、「医者なら、なんで私が病気になって、悪いことをしてる人たちはならないのか。私が病気になった理由をちゃんと教えてください」と言われます。
つまり、宗教的・伝統的な価値観に基づく説明を持ち出さないと心の底から納得できないという、ごく当たり前の心理があることに気付きました。

- それは西洋医療の範疇を超えてしまいますね。

そうですね。驚くことに、現地の伝統医はそれをちゃんと説明するんですよ。「先祖がこういうことをしたから」とか「あなた、あの木の下で寝たでしょ?」といったように。やっぱり現地の医者はその患者の先代、先々代からずっと診ていますから、これまでのいろいろなエピソードを知っているんです。だからそういったことが言えて、その説明があって初めて患者さんも納得しますし、私たちと伝統医だったら伝統医のほうを信用するんです。

- そういう世界がまだ残っているとは・・・。
そこで私は、医学を学んだ医師は、実は「万能ではない」ってことに気付きました。私たちが信じて疑わない現代医療というのは、「医者の言うことを聞けば治る」と刷り込まれている側面があって、自分も患者さんにそう接していたのですが、アフリカの人はもっと原始的で、ちゃんと疑問を持って真摯に生きているんです。人間と人間のつながりが濃く、専門職に頼らず自分たちでなんとかしたいという自尊心を持った人たちなので、真の意味で「いきいき」している。誰かに生かされていないんです。
初めは医者として彼らを助けたいと思ってアフリカへ渡りましたが、現地の人たちの「自分らしく生きる」という精神的な豊かさに惹かれて、20年以上経っても、もっともっとアフリカを知りたいと思っています。
医師はただ診療だけではなく、どうすれば人々の暮らしを
豊かにできるかを考えなければならない
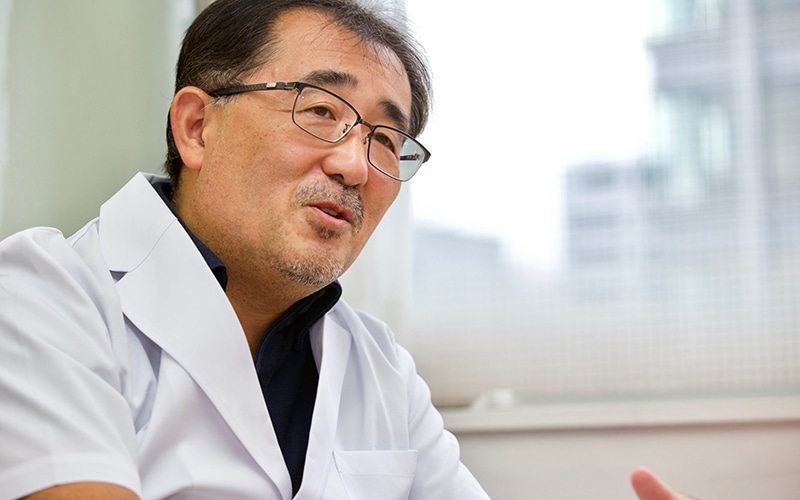

- 以来、20年以上アフリカに携わってきた杉下先生から見て、
アフリカの医療や社会はどう変化してきましたか?
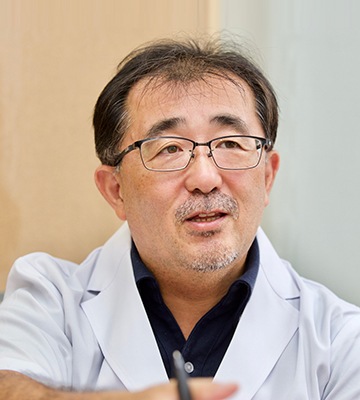
アフリカの場合、経済の発展とともに母子保健をはじめとした保健システムが強化され、さらには予防医療が浸透し、医療を取り巻く状況はずいぶんと改善しました。その結果、HIVの新規感染者も激減していますし、感染してしまった方も、多くの場合、抗ウイルス薬で発症が抑えられています。私はこれまでアフリカ20ヵ国以上でお仕事をさせていただきましたが、保健分野は急速に良くなってきているという印象がありますね。ただ、全体的には想像以上に良くなる一方で、その恩恵を受けることができない人たちが、ここ数年目立ってきたんです。例えば、障害者や高齢者、それから民族的・性的なマイノリティーといった、社会的脆弱層の人々の状況は改善していないばかりか、格差がどんどん進行している。このような現状を踏まえて、「すべての人が、予防、治療、機能回復に関するサービスを、適切で支払い可能な費用で受けられる」ことを意味する「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」を目標に支援を続けています。

こうした「健康格差」は、もはやアフリカだけの問題ではなく、日本も含む世界中の問題です。社会的弱者はアフリカにもいますが、ちゃんと社会での役割を担っていますし、たとえ身体的な機能が衰えても、持っている能力の中で人々の役に立っている実感があります。もしかすると、それってすごく豊かな社会ではないかなと思うんですよね。

- 杉下先生が、今後取り組んでいきたいことをお聞かせください。

これからの医師の役割は、「最新の診療に努めること」が大切なのは当然ですが、そのような努力の先に、「どうやったら人々の暮らしや生活を良くできるか」「社会を変えていけるのか」ということも考えなければならない時代になってきたと思います。私は昨年から東京近郊で在宅医療や精神疾患診療などのお手伝いをしながら、アフリカで感じ、考えてきた人間の自尊心や自立の精神、物に頼らない精神的な豊かさを学生の皆さんに伝えられたらと思っていますし、最終的には私たちが暮らす日本やこの地球を、「皆さんとともにどうやって美しくデザインできるのか」という課題に取り組んでいきたいと思っています。

- 杉下智彦教授
- 1990年に東北大学医学部を卒業。聖路加国際病院で外科医として勤務したあと、東北大学心臓外科医局にて心臓移植の研究を行う。1995年に青年海外協力隊として、マラウイ共和国の国立ゾンバ中央病院に赴任。3年間の活動を経て、ハーバード大学公衆衛生大学院で国際保健学を、ロンドン大学アジア・アフリカ研究大学院で医療人類学を修学。その後、タンザニア共和国モロゴロ州保健行政強化プロジェクトのリーダーを務めたのを皮切りに、国際協力機構(JICA)のシニアアドバイザーとして、アフリカを中心に世界各国の保健システム構築に関わる。現在は東京女子医科大学医学部にて国際環境・熱帯医学講座の講座主任として活躍しながら、引き続きアフリカを含め世界各国の支援を続けている。
